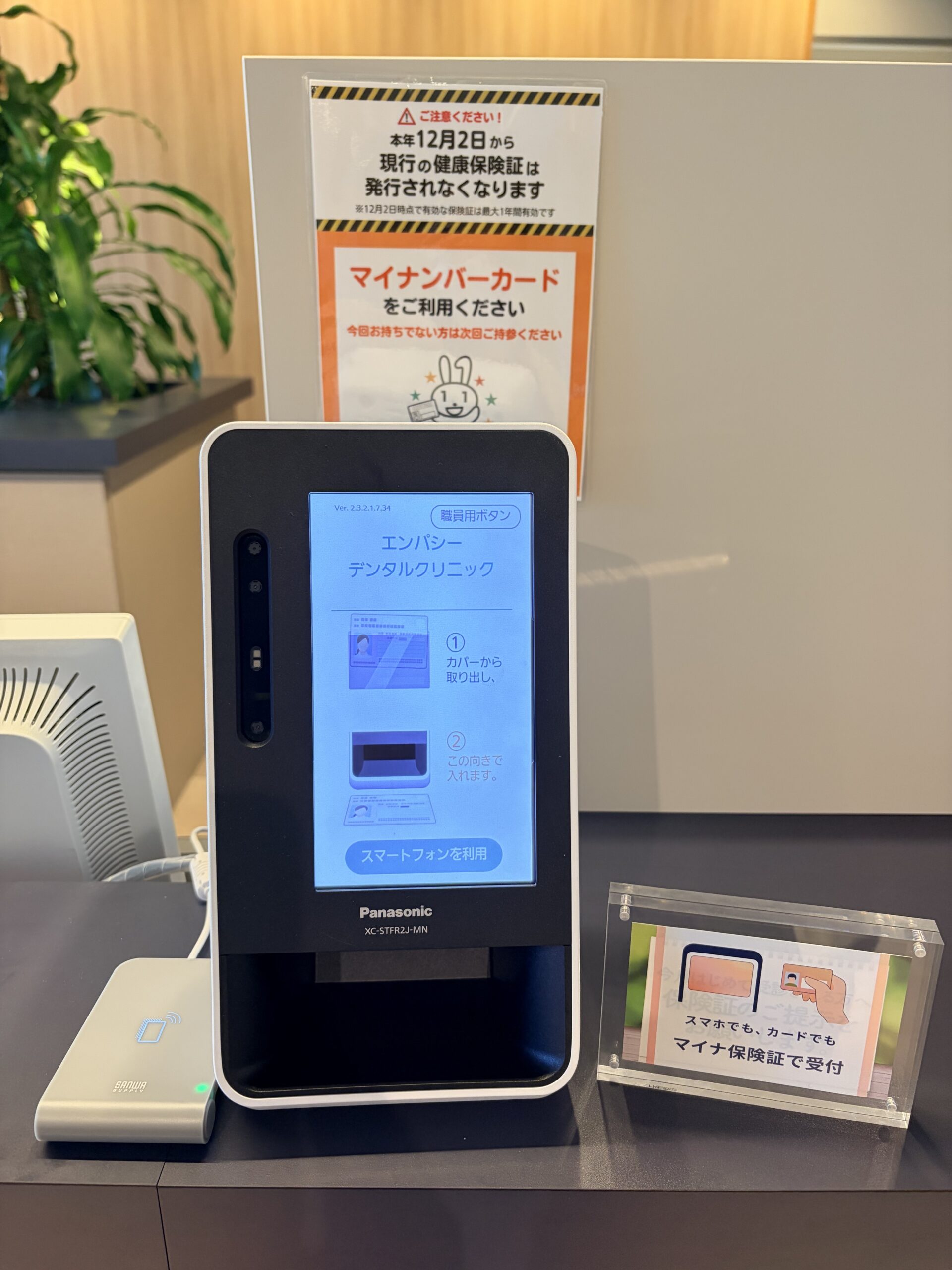目次
Q.詰め物や被せ物は劣化してしまうと聞きました。本当ですか?
A.補綴物は毎日、食事のたびに負担がかかっています。そのため経年による劣化は必ず起きてしまいます。
補綴物の経年劣化とその対策
歯の治療を終えて、補綴物(クラウンやインレー、ブリッジなど)が入ると、見た目や機能が回復し、満足している方が多いことでしょう。
しかし、補綴物はどうしても経年劣化を避けることができません。
実は、口の中の環境は非常に過酷であり、補綴物が長期間持つためには、しっかりとしたケアと経過観察が不可欠です。
1. 口の中の過酷な環境
お口の中は湿度100%、毎食ごとに10kg以上の圧がかかるといわれる過酷な環境です。
この圧力が何百回、何千回と毎日かかるため、補綴物も次第に摩耗したり、削れたりします。
また、食事をするたびに食べ物が歯に接触し、菌や汚れが付着します。
そのため、補綴物と歯の間に隙間や段差ができやすく、そこにプラークや食べかすが溜まり、むし歯や歯周病の原因となることがあります。
2. 補綴物の劣化とその影響
補綴物が経年劣化する原因には、さまざまな要因があります。
代表的なものとしては、以下のような点が挙げられます。
-
摩耗:食事の際に加わる圧力や咀嚼によって、補綴物は少しずつ摩耗していきます。特に金属ではなく、セラミックやレジン(プラスチック)の素材は摩耗が進みやすいです。
-
すき間や段差の発生:補綴物と歯との間にすき間ができると、汚れや細菌がたまりやすく、歯が再度むし歯になるリスクが高まります。段差ができると、歯磨きが難しくなり、磨き残しができやすくなります。
-
歯ぎしりやくいしばり:寝ている間に無意識に歯ぎしりをしている方や、ストレスなどでくいしばりの癖がある方は、補綴物や周囲の歯に強い負荷をかけるため、早期に傷んだり、割れたりすることがあります。
-
温度の変化:飲み物や食べ物の温度の急激な変化も、補綴物にダメージを与える要因となります。特にセラミックやコンポジットレジンは、熱膨張の違いから割れやすいことがあります。
3. 補綴物の長寿命を保つための予防方法
治療を受けた歯が長持ちするためには、予防とともに経過観察をしっかり行うことが重要です。
補綴物を入れたからといって、もはやむし歯や歯周病の心配が完全になくなるわけではありません。
むし歯や歯周病の予防、補綴物の劣化を遅らせるためには、以下の対策を実践することが必要です。
3.1. 補綴物の周りに汚れを残さない
最も重要なのは、補綴物の周囲を清潔に保つことです。
補綴物と歯との間に汚れが残ると、むし歯のリスクが高まります。
毎日の歯磨きはもちろん、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間や、補綴物と歯の接着部分の清掃が大切です。
歯間ブラシやデンタルフロスを使って、歯と補綴物の境目をきれいに保つようにしましょう。
また、定期的に歯科医院でのクリーニングを受けることも予防には欠かせません。
歯科衛生士によるプロフェッショナルなクリーニングを受けることで、自分では落としきれない汚れやプラークを除去し、健康な口腔状態を維持することができます。
3.2. トラブルが起きたらすぐに受診する
補綴物にトラブルが生じた場合、すぐに歯科医院を受診することが重要です。
たとえば、補綴物にひびが入ったり、異常を感じた場合、早期に対処することで大きな問題になる前に修理ができます。
逆に、放置しておくと補綴物の損傷が広がり、歯そのものにも影響を与えることがあります。
3.3. 自費治療を選ぶ
自費治療を選ぶことで、より精度の高い補綴物を作成することができます
。保険治療でも十分な機能性を持つ補綴物は作れますが、精度の高い自費治療を選ぶことで、補綴物の寿命が延びることが期待できます。
たとえば、セラミックや金属の素材は、耐久性が高く、また見た目も自然で、美容面にも優れています。
特に奥歯や噛み合わせに関わる部分では、自費治療でより高精度な補綴物を選ぶことが、長期的な健康を守るためには重要です。
3.4. 歯ぎしり対策
歯ぎしりやくいしばりは、補綴物や歯に大きな負担をかけ、摩耗や破損を引き起こします。
歯ぎしりの癖がある場合、就寝時にマウスピースを装着することをお勧めします。
マウスピースは、歯ぎしりの圧力を吸収し、歯や補綴物への負担を軽減します。
これにより、補綴物が長持ちし、歯の健康も守られるのです。
4. 定期的な健診の重要性
治療を受けた歯は、特に定期的なチェックが重要です。
神経を取ってしまった歯や、過去にむし歯治療を受けた歯は痛みを感じにくく、異常に気づくのが遅れがちです。
そのため、定期健診を受けることで、早期に問題を発見し、治療を早めに行うことができます。
歯科医師は、レントゲンを使って内部の状態をチェックしたり、歯茎や歯の周りを丁寧に診察して、潜在的な問題を発見します。
これにより、むし歯や歯周病が進行する前に対処でき、補綴物の寿命を延ばすことができます。
5. 歯の寿命を延ばすための新しい技術
近年、歯の寿命を延ばすために「歯の年齢診断プロ」という新しいシステムが開発されています。
このシステムでは、歯の状態を診断し、その歯がどれくらい持つかを予測することができます。
自分の歯の寿命を知ることで、治療やケアの方針をより具体的に決めることができ、予防策を強化することができます。
6. まとめ
歯の補綴治療を受けた後、補綴物が長持ちするかどうかは、患者さん自身の日々のケアや定期的な健診にかかっています。
補綴物はどうしても経年劣化を避けられませんが、適切なケアを行い、トラブルを早期に発見し、必要な処置を取ることで、その寿命を大幅に延ばすことができます。
また、自費治療を選ぶことで、より精度の高い補綴物を得ることができ、長期的に健康な口腔状態を保つことができます。
私たち歯科医師は、患者さんの歯をできるだけ長持ちさせるために全力を尽くしています。
治療後も、予防を意識したケアを続け、健康な歯を守りましょう。