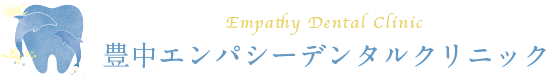目次
「歳を重ねても美味しく食べたい」「いつまでも人と楽しく話したい」──そんな願いを叶えるために、口の健康は欠かせません。
でも知らず知らずのうちに、口の機能が少しずつ衰えていくことがあります。
これを「オーラルフレイル(口腔虚弱)」と呼びます。本記事ではその定義と原因、予防・改善方法を詳しく解説します。
1 オーラルフレイルって何?
オーラルフレイルとは、口の機能が完全に低下していないものの、健口(健康なお口)と機能不全の間にある“中間的な衰え”の状態を指します。健康と要介護の間に位置する「フレイル」という概念の、口における段階です
簡単な自己チェック「OF‑5(Oral Frailty 5‑item Checklist)」の項目は以下の通り
-
歯の本数が20本未満
-
固い物が食べにくくなった
-
お茶や汁物でむせる
-
口が渇きやすい
-
滑舌が悪くなった
このうち2つ以上が当てはまると、オーラルフレイルと診断されます。
2 なぜオーラルフレイルが問題なのか?
生活の質の低下につながる
滑舌の悪化は会話のしにくさを招き、食べにくさは栄養不足や食の楽しみの喪失を導きます 。
口のトラブルは「硬い食品を避ける→やわらかい物が中心に→さらに食べにくくなる」という悪循環に陥りがちです。
要介護や死亡リスクとの関係も指摘され、咀嚼や嚥下機能の低下による栄養不足は筋力低下(サルコペニア)を引き起こし、身体機能の低下(フレイル)へとつながっていきます 。
さらに、口腔内の炎症(虫歯や歯周病)が慢性疾患(糖尿病・動脈硬化など)を悪化させるとの報告もあり、医科歯科連携による対応が重要です。
3 オーラルフレイルと「歯を長持ちさせる鉄則」
『歯を長持ちさせる鉄則』では、日常の口腔ケアと定期的なプロのチェックを重視していますが、これはオーラルフレイルの予防・改善にも有効です。
鉄則① 毎日ていねいな歯磨きをする
歯の本数を維持するには、虫歯・歯周病の予防が基本。歯ブラシ+フロス・歯間ブラシの併用と、フッ素入り歯磨き粉の使用が推奨されます(1日5分程度の丁寧磨き)
鉄則② 定期的な歯科検診を欠かさない
プロによるクリーニングと機能チェックにより、早期治療・生活改善が可能になります。特に年1~2回、フレイル兆候が見つかったら半年ごとの通院がおすすめです。
鉄則③ 口腔運動(口の体操)を習慣化す
「パタカラ体操」や「あいうべ体操」は、唇・舌・のどの筋力を高め、噛む・飲む・話す機能を支えます。
4 具体的なオーラルフレイル対策
A. 自宅でできるセルフチェックと習慣
-
OF‑5セルフチェックを定期的に実施(項目を紙やアプリで記録)。
-
歯磨き+フロス習慣:夜寝る前は念入りに。
-
舌ケア:舌苔(舌の汚れ)を軽く舌ブラシで除去し、口臭・乾きの改善を図る。
B. 口腔トレーニング
-
パタカラ体操:「パ・タ・カ・ラ」を1日10セット。
-
あいうべ体操:舌や唇を大きく動かし、口腔全体の毎日トレーニングに。
-
咀嚼トレーニング:硬めの食材(れんこん・ゴボウ・皮付き野菜)やガムで咀嚼力アップ
C. 食と栄養に気を配る
-
バランスの摂れた食事を心がけ、特にたんぱく質をしっかり摂取(体重1kg当たり1.0g以上)
-
一人で食べず、家族や友人との「共食」で食欲と社会性を維持しましょう。
D. 定期的なプロのチェック
-
歯医者さんに定期健診で歯数・虫歯・歯周病状況を共有し、必要に応じて補綴(義歯・インプラントなど)を検討。
-
オーラルフレイルチェックも実施してもらい、機能改善のアドバイスを受ける
5 オーラルフレイル予防 × 全身フレイル予防の連携
オーラルフレイルの改善は、以下のような全身のフレイル対策とも密接に結びついています。
-
適度な運動療法との併用で、筋肉や身体機能の維持が促されます。
-
食事改善+口腔機能強化により、低栄養や咳込による誤嚥性肺炎の予防にもつながります。