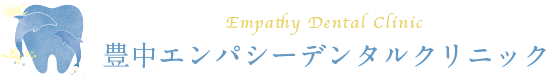目次
Q.子どもの噛み合わせが乱れていると、どうなるの?
A.脳機能や顔面の発育に影響を及ぼします。
子どもの成長と噛み合わせの重要性
1. はじめに
子どもの成長にとって、噛み合わせの乱れは見過ごせない重要な問題です。
噛み合わせが悪いこと自体が単なる症状に過ぎず、その背後にはさまざまな身体的・精神的な問題が潜んでいる可能性があります。
今回は、噛み合わせの乱れが子どもの成長に与えるリスクと、その予防や対策について詳しく解説します。
2. 噛み合わせの乱れと発育の関係
小児期におけるお口周りの機能バランスが悪いと、脳機能や顔面の発育に悪影響を及ぼし、それが噛み合わせの乱れとして表れることがあります。
これは、単に歯並びが悪くなるだけでなく、以下のような広範な影響を及ぼします。
① 脳機能への影響
噛み合わせが悪いと、顎の正しい発達が妨げられ、脳への刺激が不足することがあります。
その結果、以下のような問題が生じる可能性があります。
・学業不良
・注意力の低下
・多動症状
・感情の不安定さ
・攻撃性や頑固さの増加
②顔面の発育への影響
お口周りの筋肉や舌の発達が不十分な場合、顎や顔の骨の成長にも影響が出ます。例えば、
・顎が小さくなることによる歯並びの乱れ
・顔の非対称な成長
・姿勢の悪化
などがあげられます。
3. 悪い習慣と噛み合わせの乱れ
噛み合わせの乱れの原因として、幼少期の生活習慣が大きく関与しています。
特に以下のような習慣があると、噛み合わせが悪化しやすくなります。
①指吸い・おしゃぶりの長期使用
指吸いやおしゃぶりを長期間続けると、前歯が前方に押し出されることで「開咬(かいこう)」と呼ばれる状態になりやすくなります。
開咬は、食事の際にうまく噛めないだけでなく、発音の問題や口呼吸の原因にもなります。
②口呼吸
口呼吸が習慣化すると、口腔内が乾燥し、虫歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、上顎が狭くなり歯並びが悪くなります。
また、口を開けたままの状態が続くと、顔の筋肉の発達にも悪影響を及ぼします。
③舌の使い方の問題
舌の位置が正しくないと、歯に異常な力がかかり、歯並びが乱れやすくなります。
特に、舌を前に押し出す「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」があると、前歯が開いてしまう原因となります。
④姿勢の悪さ
姿勢が悪いと、顎の位置がズレて噛み合わせに影響を与えます。
特に、長時間スマートフォンやタブレットを使用することによる猫背は、顎関節や噛み合わせの不調を引き起こす可能性があります。
4. 噛み合わせの乱れが引き起こす健康問題
噛み合わせの乱れは、単なる見た目の問題ではなく、全身の健康にも影響を及ぼします。
①呼吸機能への影響
噛み合わせが悪いと気道が狭くなり、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まる可能性があります。特に、口呼吸が習慣化すると、睡眠の質が低下し、成長ホルモンの分泌が妨げられます。
②消化機能への影響
噛み合わせが悪いと、食べ物を十分に噛むことができず、消化器官に負担がかかります。その結果、胃腸の不調や栄養吸収の低下につながります。
③精神的な影響
歯並びが悪いことがコンプレックスになり、自己肯定感の低下を招くことがあります。特に、思春期になると歯並びが原因で笑うことを避けるようになったり、対人関係に消極的になったりすることがあります。
5. 適切な矯正治療の重要性
噛み合わせの問題は、早期に適切な矯正治療を行うことで改善できます。
① 矯正治療の適切なタイミング
子どもの矯正治療には、乳歯列期(3~6歳)、混合歯列期(6~12歳)、永久歯列期(12歳以降)の3つの段階があります。それぞれの段階で適した治療方法があります。
-
乳歯列期:指吸いや口呼吸の改善、舌の正しい使い方を指導する。
-
混合歯列期:歯並びを整えるための装置を使用し、顎の成長をコントロールする。
-
永久歯列期:本格的なワイヤー矯正やマウスピース矯正を行う。
②予防的アプローチ
噛み合わせの問題を未然に防ぐためには、以下のような取り組みが重要です。
-
正しい姿勢を保つ
-
口を閉じて鼻呼吸を意識する
-
硬いものをしっかり噛む習慣をつける
-
舌の正しい使い方を身につける
6. まとめ
噛み合わせの乱れは、単なる歯並びの問題にとどまらず、子どもの成長や健康に多大な影響を及ぼします。
適切なタイミングでの矯正治療や生活習慣の見直しにより、健全な発育を促すことができます。保護者として、子どもの健康な成長を支えるために、早めの対策を講じることが大切です。
豊中・少路の歯科医院 エンパシーデンタルクリニック
お約束はWebまたは通話料無料のお電話(0800-805-1180)でもお取りできます。
定期健診や気になる症状などもございましたらお気軽にご相談ください。