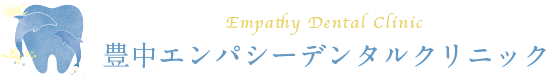目次
私たちの毎日の生活に欠かせない「歯」。
食べ物を噛む、発音する、表情をつくる――そんな当たり前の動作を支えてくれる大切な器官です。
でも、「歯の中ってどうなってるの?」「虫歯はどこからできるの?」といった質問に即答できる方は少ないのではないでしょうか?
今回は、歯の構造について、できるだけわかりやすく、詳しく解説します。
「歯を守ることの大切さ」が、きっと今よりもっと実感できるようになりますよ!
1. 歯は「外からは見えない部分」がとても大切
歯は、白く見える部分だけではありません。
実は、歯は大きく分けて以下の2つのパーツから成り立っています。
-
歯冠(しかん):お口の中に見える「歯の頭」の部分
-
歯根(しこん):歯ぐきの中に埋まっている「歯の根」の部分
見えているのはほんの一部。
歯の根っこは、顎の骨にしっかりと埋まっていて、歯が抜けたり動いたりしないように支えています。
2. 歯の内部構造|4つの層からできている!
歯の断面を輪切りにすると、以下のような構造になっています。
【① エナメル質(エナメルしつ)】
-
歯の一番外側にある、とても硬い組織
-
人体で最も硬い組織(なんと骨より硬い!)
-
白くてつやのある部分で、歯を守る「よろい」のような役割
ただし、再生しない組織のため、一度削れたり虫歯になってしまうと元には戻りません。
【② 象牙質(ぞうげしつ)】
-
エナメル質の内側にある黄色みがかった組織
-
骨に近い性質で、やや柔らかく、虫歯が進行しやすい
-
加齢や刺激によって“知覚過敏”を起こしやすい部分でもある
象牙質には小さな管(象牙細管)が無数に走っており、刺激が神経に伝わりやすい構造になっています。
【③ 歯髄(しずい)】
-
歯の中心部にある「神経」や「血管」が通る部分
-
痛みを感じる場所でもあり、歯の「命」といえる部位
-
虫歯がここまで達すると、強い痛み(神経の炎症)を感じることが多い
歯髄まで虫歯が進行すると、根管治療(歯の神経を取る治療)が必要になるケースが多くなります。
【④ セメント質(セメントしつ)】
-
歯根の表面を覆っている組織
-
歯根膜(しこんまく)と一緒に、歯と顎の骨をつなぐ役割
-
見えない部分にありますが、歯の安定性に欠かせない組織です
3. 歯を支える「歯周組織」も重要!
歯は、単独で立っているわけではありません。
周囲の組織と一体になって、はじめてしっかりと機能しています。
この「歯を支える周りの組織」のことを歯周組織と呼びます。以下のような構造で成り立っています。
■ 歯肉(しにく)=歯ぐき
-
歯の周囲を覆う柔らかい組織
-
健康な歯肉はピンク色で引き締まっている
-
炎症が起きると赤く腫れたり、出血したりする(=歯肉炎)
■ 歯根膜(しこんまく)
-
歯根と顎の骨の間にある繊維性の膜
-
クッションのような役割があり、噛んだ時の衝撃を吸収する
-
歯が動く感覚を脳に伝えるセンサーの役目もあります
■ セメント質
-
前述のとおり、歯根を覆う組織で、歯根膜が付着する土台
■ 歯槽骨(しそうこつ)
-
歯を支えている「顎の骨」のこと
-
歯周病が進行すると、この骨が溶けてしまい、歯がグラグラになる
4. 歯の構造を守るためにできること
では、大切な歯を長く健康に保つためには、どのようなケアが必要なのでしょうか?
● 正しいブラッシング
歯の表面だけでなく、歯と歯の間や歯ぐきの境目までしっかり磨くことが重要です。
フロスや歯間ブラシの併用もおすすめです。
● 定期的な歯科検診
歯の構造は自分では見えない部分が多いため、歯科医院での定期チェックが欠かせません。
初期の虫歯や歯周病を早期に発見できます。
● 食生活の見直し
甘いものや酸っぱい飲食物は、エナメル質を弱める原因になります。
食後は早めの歯磨きを心がけましょう。
5. 歯は一生のパートナー
歯の構造はとても緻密で、驚くほどよくできた仕組みです。
でも、一度失われた歯や神経は、基本的に元には戻りません。
だからこそ、日頃の予防が本当に大切です。
当院では、虫歯や歯周病の治療はもちろん、歯を守るための予防処置や定期メンテナンスにも力を入れています。
気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。